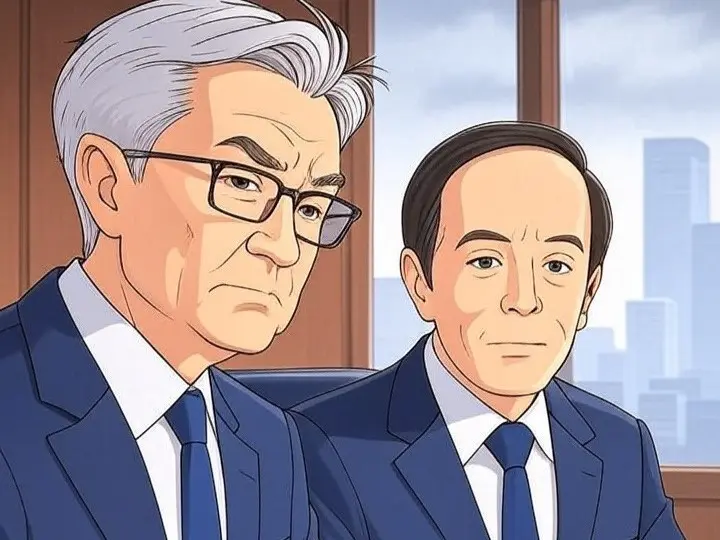米雇用減速に「予防の利下げ」 日銀は出口戦略を模索
米国の金融政策を担う連邦準備制度理事会(FRB)は18日の連邦公開市場委員会(FOMC)で、政策金利を0・25%引き下げ、4・00~4・25%の誘導目標とした。物価上昇率が依然として目標の2%を上回るなかでの利下げ決定は、物価と雇用の双方の安定を使命とする「デュアルマンデート」との矛盾を映し出している。
背景には米雇用市場の減速がある。8月の非農業部門雇用者数(NFP)は前月比2万2000人増と大幅に鈍化(前回は7万5000人増)。失業率も4・3%に悪化した。一方、消費者物価指数(CPI)は前年同月比2・9%、食料とエネルギーを除くコアCPIも3・1%と依然高止まりしている。インフレ圧力が根強い中で、雇用維持に必要な人員増を下回る水準が続けば景気減速が連鎖しかねない。
米FRBのパウエル議長は会見で「今日の決定は〝リスク管理の利下げ〟と考えてよいだろう」と語った。今回の利下げは危機対応ではなく、予防的な措置との位置付けだ。特に若年層やマイノリティ層の就業機会が狭まりつつある現状を踏まえ、「労働市場の下振れリスク」を重視した格好である。
利下げがインフレを加速させるとの懸念もあるが、FRBは①関税要因の物価上昇は一時的②雇用減速が賃金や需要を抑える③長期のインフレ期待は2%に安定――と整理。物価よりも雇用リスクが大きいと判断した。もっとも理事らの見通しは分散しており、今後の利下げ回数を巡って見方が割れていた。今後についてFRBは「政策はあらかじめ決められたものではなく、会合ごとに判断する」としており、不透明感は残る。
一方、日本銀行は19日の金融政策決定会合で、政策金利を0・5%に据え置くことを決定した。ただ、7対2と反対票が2票入った点が市場を驚かせ、10月にも利上げに踏み切るとの観測が浮上している。
さらに日銀は、簿価ベースで37兆円を保有する上場投資信託(ETF)と不動産投資信託(Jリート)の売却開始を発表した。年間3300億円ペースでの売却となり、完了には長い時間を要する見通しだ。売却額は市場売買代金の0・05%程度となり、市場への影響は小さい。「スピードより市場安定を優先した」(市場関係者)との見方が出ている。
日銀は2021年からETF購入を減額し、24年には新規購入を停止。今回ついに売却開始を決め、株式市場への介入から徐々に手を引く「出口戦略」に踏み出した。日経平均株価が最高値圏にある今を「売却の好機」と判断したとの声もある。
米国は高止まりするインフレと弱まりつつある雇用の板挟み、日本は長年続いた異例の緩和策からの脱却という課題を抱える。両国の政策判断は世界市場に直結しており、その行方は引き続き注視される。
<メモ>中央銀行のデュアル・マンデート(使命)とは?
| 米国・連邦準備制度理事会(FRB) | ①物価の安定 ②最大限の雇用 |
| 日本銀行(BOJ) | ①物価の安定 ②金融システムの安定 |
| 欧州中央銀行(ECB) | 物価の安定 |
| 中国人民銀行(PBOC) | ①物価の安定 ②経済成長推進 ③雇用促進 ④国際収支のバランス維持 |