本紙編集長であり、もりぐち夢・みらい大使のU.K.こと楠雄二朗は、この地域の最大の魅力は〝人〟であると断言する。そんな守口・門真エリアで輝きを放つ人物に迫る「みらいびと」。今回はこれからの若手経営者に送る特別編。「人を大切にする経営学会」の坂本光司会長。「人を大切にする企業が増えれば、この国の未来は大きく変わる」と断言するその真意に迫る。

利益偏重社会への警鐘「人を幸せにする」真の経営とは?
─「人を大切にする経営学会」を始められたきっかけは?
大学卒業後、最初に入った職場は公的サービスを提供するところで、中小企業と関わる仕事に配属されました。さまざまな中小企業を見て、「こんな立派な会社もあるんだ」と感じる一方、政策支援が問題のある企業ばかりに流れ、本当に立派な会社は行政と組まないため、光が当たらない現状に疑問を持ちました。一度きりの人生、多くの人が幸せを実感できる社会にしたいという思いが、私の活動の原点です。
─先生の著書で「人件費は、社員が普通の生活を送るために必要な支出である」という言葉に感銘を受けました。しかし経済界では受け入れられにくい考えでは?
当時は「イケイケどんどん、人件費はコストだ」という時代でしたから。提唱当初は「理解されにくい」「おかしな宗教では」とまで言われたことも。でも、人間は誰もが本来的に「人を幸せにしたい」という気持ちを持っていると私は思っています。それを表現するチャンスや勇気があるかどうかの違いです。もちろん、あちこちから叩かれました。例えば、遠方から相談に来た中小企業の社長に、役所の時間外に喫茶店で対応していたら、「金でもせびってるのでは」とか「お茶代をもらってるんじゃないか」などと陰口をたたかれたことも。でも、忙しすぎて気にする余裕もなく、むしろその忙しさが私を成長させてくれました。
─大企業のリストラにも非常に厳しい見方をされていますね。
大手電機メーカーを例に挙げれば、何千億円という利益を出していながら希望退職を募る。私にはあり得ない話です。大手自動車メーカーでは、厳しい状況の中、退任役員4人に4~5億円もの退職慰労金を支払いながら、2万人のリストラを進めている。こんな計画が本当にあり得るのかと。マスコミも、リストラをまるで正しいことのように報じる傾向があります。私は常に「経営とは人を幸せにすることだ」と言っています。路頭に迷って幸せになる人など、世の中に一人もいません。

本当の力は、人を幸せにする力
─今の経営学や教育、マスコミが業績至上主義を助長していると批判されていますが。
多くの人が企業経営の目的は業績だと教えられ、それがノーベル経済学賞を受賞するような人にも評価されてきた。でも私は違う。経営の目的は、関係する人を幸せにすること。業績はそのための「手段」であって、目的ではありません。社員の首を切る前に、まず経営陣が「自分の腹を切る」べき。社員を路頭に迷わせるなら、会社は潰すべきだとも言っています。
─新刊「人を大切にする経営学用語辞典」も非常にユニークですね。
長年の夢が実現したんです。従来の辞書には「人件費はコスト」とありますが、私の辞書では「社員と家族が普通の生活を送るために必要な支出」と定義しています。社長も「最高権力者」ではなく、「社長という仕事をしている社員」と記しています。利益率も「高い方がいい」ではなく「ほどほどがいい」と。私は、2~3%の利益率でも社会貢献し、障がい者や高齢者を雇用し、年を取ってもきちんと給料を払う会社の方が、はるかに良い会社だと思っています。
─そうした考えがようやく時代に受け入れられつつあると感じている。
まだ「ING」という感じですね。これまで8500社以上の現場を回ってきましたが、「もう一度行きたい」と思える、社員や家族が幸せを実感できる会社は、1割ほどしかありません。でも、昔よりは増えています。「異常が長く続くと、異常が正常に見える」という錯覚に陥りがちですが、少しずつ正しいことが理解されるようになってきています。
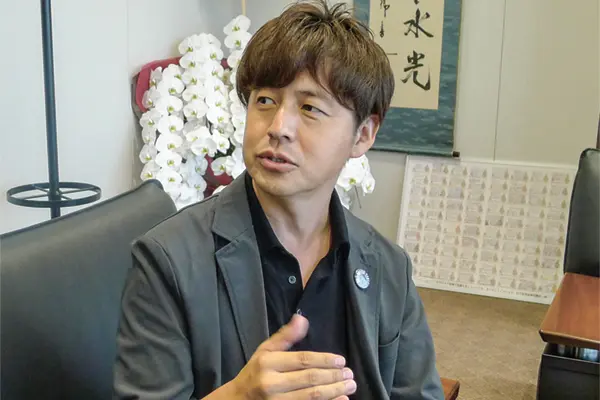
─最後に、若い世代に向けてメッセージを。
まず一つは、「今日を精一杯」「弱き人々に寄り添う」「本当の力は、人を打ち負かす力ではなく、人を幸せにする力である」「大切な人の夢や希望、欲求を満たす喜び」こそが、人間の究極の幸せだと考えています。そうした喜びを多くの人が感じられる社会になれば、この国は見事に再生するはず。そのためには、一人ひとりの意識を変えることが重要です。政治に期待するのではなく、自分たちの価値観を変える。それがより良い世の中につながるはずです。
