大阪を代表する伝統的な盆踊り「河内音頭」。この音頭取りとして広く知られる河内家菊水丸さんは、万博への思いがひときわ強いことでも有名だ。きっかけは1970年の大阪万博。全国の民謡が披露される中、大好きな河内音頭の出番はなかった。あれか55年。ついに、大阪・関西万博で夢をかなえる菊水丸さんに、阪本晋治が迫る。(佛崎一成)
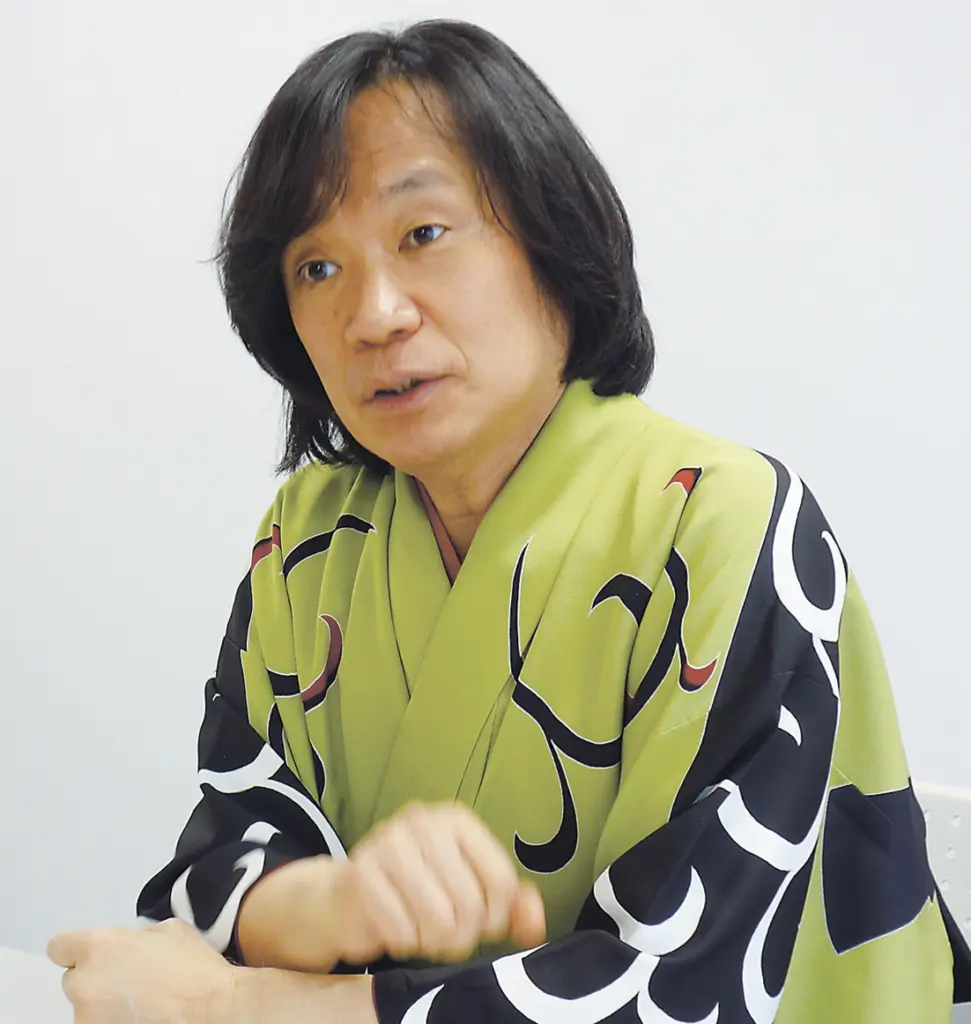
─河内音頭にふれた最初の記憶は。
生まれ育った大阪・八尾市では、河内音頭は生活の一部だった。加えて、父が音頭取りの師匠だったので、自然と河内音頭に囲まれて育った。でもね、家庭環境はちょっと複雑で、母はピアノの先生だったが、小1のときに両親が離婚してしまった。
─そこからどうやって音頭の道に。
子どものころから、子守唄のように河内音頭を聞いて育ったので、「どうしても父のもとで学びたい」と母にお願いした。でも母は迷っていた。『お父さんに会いたいから行くんじゃないの?』と。僕は「河内音頭を習いたいから行くんや!」と何度も説得した。母もしばらく考えてから「お父さんに会いに行くのではなく、河内音頭を習いに行くというのなら行ってもいい」と。
─音頭取りとして、初めて櫓(やぐら)の上に立ったときの記憶は。
昭和48年、小4の夏だった。東大阪市の近鉄弥刀(みと)駅近くの盆踊り大会が初舞台だ。櫓の上に上がると紅白の幕に遮られ、小学生で背の小さい僕からは下の様子が見えない。だから、普段のけいこと変わらない感覚で歌えた。櫓から降りて「こんなに人おったんか!」とびっくりしたくらいだ(笑)。
あのときの快感が、僕を河内音頭の道へと突き動かしていった。
いつか万博の舞台で
─その後は順調に。
実はそうでもなく、小5の冬に母から突然「来年からけいこに行ってはダメ」と告げられてしまった。やっぱりね、僕と父は親子だから、どうしてもきっちり〝師匠と弟子〟の関係にならなかった。それが母の耳にも入った。
でも河内音頭をどうしても続けたくて、中学に入ってから別の師匠のもとに習いに行った。新しい師匠は厳しかった父とは違い、楽しい人。この出会いが、僕の河内音頭人生を再び動かした。
─高校時代には、すでに本格的に活動を。
高校3年のとき、吉本興業のなんば花月で初舞台を踏みました。そのとき「将来の目標は?」と聞かれて、迷わずこう答えた。「いつか万博の舞台で河内音頭を歌いたい」と。
70年万博の悔しさ
─菊水丸師匠は万博に特別な思いがある。そのきっかけとなった70年万博でのエピソードを教えてほしい。
当時、私は小1か小2だった。ちょっと話がずれるが、3月の開幕時は1年生で、4月以降は学年が上がるから2年生になった。だから、みんな70年万博で「何年生やった?」と聞かれると説明しにくい。
そこで当時の松井一郎知事に「万博は4月からにしてほしい。思い出を語るのにややこしい」と伝えた。すると松井知事は「なるほど、それはそうやな」と考えてくれて4月以降になった…と、勝手に思っていますが。
話を戻すと、70年万博には、母に頼み込んで何度も通った思い出がある。アメリカ館の〝月の石〟を見るため炎天下の中で4時間並んだ。そしてようやく順番が来たと思ったら、「立ち止まらないでください」と、流れる人混みに押され、次の瞬間にはもう扉の外だった(笑)。
それでも何とかアメリカ館のスタンプだけは手に入れることができた。ブルガリア館や日本館のスタンプを手に入れた友達はいたけど、アメリカ館のスタンプは子どもたちの中でステータスだったからだ。
あとは、イタリア館で初めてグラタンを食べたのを覚えている。当時、オーブンなんて家庭になかった時代だ。一般的にグラタンが食べられるまでには、そこから十数年も後のことだ。食べるもの、飲むものすべてに衝撃を受けたことを記憶している。
でも、それより忘れられないことがあった。とても悔しい思い出だ。
─それは何か。
太陽の塔のある「お祭り広場」で、北海道から九州・沖縄まで全国の民謡が披露されるイベントがあった。幼い僕はワクワクしながら河内音頭の出番を待っていた。しかし、最後まで出番が来ることはなかった。
全国の伝統芸能が紹介されていたのに、大阪の代表的な庶民文化であるはずの河内音頭が、その舞台にすら立てない。子ども心に、それが不思議だったし、悔しくて仕方なかった。
─なるほど。それで万博で河内音頭を踊ることが目標になったのか。
1980年の初舞台以降、行く先々で「目標は?」と聞かれたとき、必ず「万博で河内音頭を踊ることです」と言い続けた。
そうしたらチャンスが巡ってきた。88年にオーストラリアのブリスベン万博で、「日本館の祭事に出てくれ」という依頼が入った。河内音頭を万博で披露するという夢が実現した瞬間だった。
その後、2005年に愛知・名古屋で開かれた愛・地球博でも歌う機会を得て、10年の上海万博では万博史上初の試みとして都市単位で参加できる「ベストシティ実践区」が設けられ、日本から唯一出展した大阪館で、当時の橋下徹府知事の依頼を受けて「日中友好音頭」を口演した。
万博で河内音頭を披露する夢がかない、もはや思い残すことはないと思っていた。そんな矢先、大阪に再び万博がやって来ることになった。

人生の集大成
─万博誘致が決まったときの心境は。
50年前、万博の舞台に立つことすら許されなかった河内音頭の悔しさをずっと胸に抱いていた中で、僕の50年越しのリベンジのチャンスが巡ってきたと思った。まさに人生の集大成だ。河内音頭の出番を確保するため、すぐに吉村洋文知事に会いに行った。
─そこでどんな話を。
「知事、70年万博で河内音頭が呼ばれなかったのは知ってはりますか?」って。そうしたら吉村知事はちょっと驚いた顔をして、「そうなんですか?」と。
そして吉村知事から「大阪・関西万博で河内音頭をお願いします」という言葉を取り付けた。もうね、震えましたよ。「50年の悲願がついにかなうんや」って。
─そんなにスムーズに。
ただ公式な場での発表がほしくて、その後も気を抜かなかった。そこで僕は23年6月の盆踊りツアーの出陣式に、吉村知事にお越し頂いたんです。
出陣式の最後に、僕が「小1のとき、70年万博で河内音頭が呼ばれなかった悔しさを大阪・関西万博で実現したい』と熱弁した。すると知事がマイクを持って「来年の万博で河内音頭を歌っていただきたい。正式にオファーします」ということを言ってくれたんです。震えましたね。
─ところで今度の万博。夢洲での開催については否定的な声もある。
70年万博が千里の山の上であったから、勘違いしている人もいるかもしれないが、本来は万博というものは水辺で開催するのが原則なんです。パリ万博ではセーヌ川、ドバイ万博や上海万博も水辺だったでしょう。だから70年万博も本当は南港(現在の咲洲エリア)で開催される予定だった。
ところが、当時の左藤義詮府知事が千里ニュータウンの開発を進めるために「万博を千里でやるべきだ」と主張し、山の上(千里)に会場が決まった経緯がある。これは万博の歴史でも異例の決定だったんです。それが証拠に、万博は基本的に水辺でやるものだからという理由で、博覧会協会から一度ダメと言われている。それでも特例で山の上で開催されることが認められた。
だから、当時の異例を認めてくれた博覧会協会へのお礼というか。本来の水辺開催と言う意味では、今回こそが第1回目と言ってもいいという感覚でいる。あくまで僕の意見だが。
─大阪・関西万博ではどんなステージを予定しているのか。
7月28日の「なにわの日」に決まった。万博会場の野外ステージ「EXPOアリーナ」で実施する。小1のときから抱き続けた夢が、半世紀を経てついに完結する。夢だった大阪での万博の舞台で、河内音頭を存分に響かせたい。

河内家菊水丸(かわちや きくすいまる、1963年生まれ)
大阪府八尾市出身の伝統河内音頭継承者。活動期間は主に6月〜9月。各地の盆踊りやイベントに数多く出演して人気を博す。冬場は、京都府南山城村の自宅地下資料室で滅んだ外題と節まわしの復活への研究を行う。1992年、皇太子殿下※現・天皇陛下に河内音頭をご披露する。河内音頭の第一人者として、多方面で影響力を持つ文化人。

