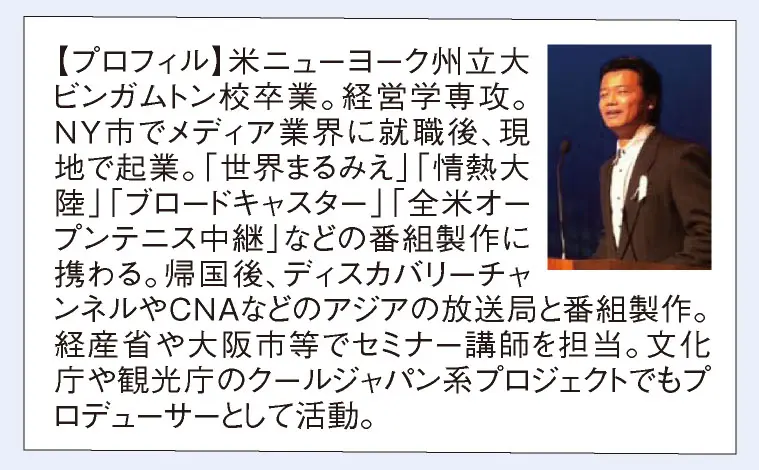岡野 健将
ネットフリックスが2026年のWBC(野球の世界大会)で日本の独占放映権を獲得した。これに対し、日本中が困惑しているのを見るのは滑稽だ。
最も高い金額を支払う者が放映権を獲得するのは当たり前なのに、それが理解できない人があまりにも多い。特にそのような声が野球界やビジネス界から上がるとは…。日本が国際マーケットから取り残されていることを痛烈に感じてしまう。
米国を筆頭に世界のスポーツコンテンツの放映権料はうなぎ登りだ。このため、地上波テレビからケーブルや衛星放送などの有料放送、そして昨今のストリーミング配信へとコンテンツの視聴チャンネルは常に変化している。日本だけがいつまでも地上波が放送するものとズレた意識を持ち続けてきただけなのだ。
国内でも、野球以外でJリーグがDAZNと放映権契約を結んでおり、23年から11年間で総額約2395億円を受け取る。国内人気でプロ野球に及ばないサッカーですら、このくらいの額になる。Jリーグ創成期から一緒に歩んできたスカパーがあっさり切られたのもビジネスとしては当然だ。
同じサッカーでも英国プレミアリーグの放映権収入(22─25年)は、国内外を合わせて約1兆6434億円。この巨額収入はスカイスポーツ、BTスポーツ、アマゾンなどの放送事業者から得られる。
米国でMLBより人気のNBAの放映権料は25─26シーズンから始まる11年間でNBC、ESPN、アマゾンの3社から総額760億㌦(約11兆8380億円)を得る。
そのNBAの日本の放映権は25─26シーズンよりアマゾンが獲得し、プライムビデオで配信される。これに伴い、25年7月末で「NBA Rakuten」がサービス終了し、WOWOWも24─25シーズンで終了した。
NBAより人気が落ちるMLBの放映権料は、ESPN、FOX、TBSなどの全米テレビ局と年間総額約17億6000万㌦(約2380億円)という7年間の契約を結んでいる。それ以外に、ロサンゼルス・ドジャースであれば、地元テレビ局から年間約1億9600万㌦(約290億円)もの放映権収入を得る。
これらの放映権料を年平均で見ると、Jリーグが200億円、プレミアリーグは5000億円、NBAが1兆円、MLBが2380億円、ドジャースの地元テレビ局ですら年間300億円近く払っている。
神戸サンテレビが阪神戦の放映権に300億円払っていることを想像してみてほしい。ちなみにロサンゼルス市の人口は400万人弱。サンテレビの視聴可能エリアの人口は1700万人だ。
これがスポーツコンテンツビジネスの世界基準だ。今や金の稼げるコンテンツに育ったWBCの放映権料が30億円から150億円になったとしても、それほど驚くことではないのがわかってもらえるのではないか。
世界的にテレビ市場の規模が米国以外でトップクラスにある日本が、各局相乗りのコンソーシアムですら150億円を払えない。つまり、そのビジネスモデル自体がすでに時代遅れであることに気づくべきなのだ。
自分たちがWBCの日本の興業を取り仕切っていると勘違いしていたある新聞社が、いかに世界のすう勢やグローバルビジネスを理解していないかが明確になり、また自分たちが思うほど存在感も価値もなかったことがはっきりしたのは良いことかもしれない。
実際、月額1000円弱を払ってネットフリックスに加入すれば、WBCの全試合を視聴できるし、それくらい払って視聴するだけの価値のあるコンテンツだと思うが、ネガティブなコメントを発している人たちはそう思わないのだろうか?
それとも、それすら払えないほどの貧困者がこの国には多くいるのか? もしそうだとすれば、その方がより大きな問題だ。